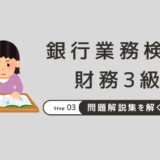銀行業務検定とは、簡単にいうと「金融業界に関する基本的な知識を評価する試験」です。金融業界に就職した新社会人が日常業務で必要な知識を身につけることができるため、多くの企業で取得必須資格&昇格要件となっています。1968年から開始されており、累計の受験申込者数が1,000万人を超える歴史ある試験です。銀行業務検定協会HPでは以下のように掲載されています。気になる方はご参照ください。
現在、以下のような23系統36種目の試験が実施されております。
青字になっている資格名をクリックすると、各資格の紹介ページに移動します。
その中でも「財務3級」は財務の分野(具体的な内容は試験内容、試験範囲に書いてあります)に特化した試験です。財務諸表の各書類に関して、それぞれが意図する内容や具体的な勘定科目、論点について問われます。証券外務員二種や金融コンプライアンス・オフィサー2級と同じく、多くの銀行で取得必須資格となっています。
ここ数年の合格率は以下の通りです。実施回によってばらつきはあるものの、おおよそ30%程度が合格しています。
| 試験実施回 | 合格率 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 27.09% | 8,265人 | 7,135人 | 1,933人 |
| 2022年3月 | 26.48% | 9,070人 | 7,700人 | 2,039人 |
| 2021年6月 | 34.23% | 11,058人 | 9,712人 | 3,324人 |
| 2021年3月 | 41.55% | 10,656人 | 9,339人 | 3,880人 |
| 2020年10月 | 30.95% | 13,767人 | 12,268人 | 3,797人 |
| 2019年6月 | 33.14% | 16,285人 | 13,863人 | 4,594人 |
| 2019年3月 | 39.54% | 19,739人 | 16,716人 | 6,609人 |
2022年6月試験における業態別の成績は以下の通りです(年齢・勤続年数は受験者の平均です)。
| 都銀・特銀 | 地銀 | 信託 | 第二地銀 | 信金 | 信組 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者数(人) 応募比率(%) | 293 3.55 | 2,089 25.28 | 102 1.23 | 655 7.92 | 3,150 38.11 | 550 6.65 |
| 受験者数(人) 受験率(%) | 278 94.88 | 1,844 88.27 | 80 78.43 | 525 80.15 | 2,770 87.94 | 482 87.64 |
| 合格者数(人) 合格率(%) | 166 59.71 | 568 30.80 | 37 46.25 | 139 26.48 | 632 22.82 | 57 11.83 |
| 平均点(点) | 62.48 | 48.67 | 55.63 | 46.66 | 44.48 | 40.12 |
| 年齢(歳) | 23.8 | 26.9 | 30.1 | 28.2 | 28.6 | 31.2 |
| 勤続年数(年) | 1.1 | 4.3 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 9.3 |
| 信連・農協 | 労金 | 生保・損保 | 証券 | 郵政 | 他団体・個人 | 全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者数 応募比率 | 481 5.82 | 17 0.21 | 110 1.33 | 12 0.15 | 29 0.35 | 777 9.40 | 8,265 100.00 |
| 受験者数 受験率 | 436 90.64 | 14 82.35 | 82 74.55 | 12 100.0 | 26 89.66 | 586 75.42 | 7,135 86.33 |
| 合格者数 合格率 | 103 23.62 | 3 21.43 | 17 20.73 | 4 33.33 | 3 11.54 | 204 34.81 | 1,933 27.09 |
| 平均点 | 44.77 | 45.00 | 42.95 | 47.83 | 37.62 | 50.97 | 46.77 |
| 年齢 | 33.4 | 32.4 | 30.9 | 30.3 | 43.5 | 33.1 | 28.9 |
| 勤続年数 | 10.7 | 10.7 | 8.1 | 13.5 | 18.8 | 8.7 | 6.5 |
合格率は高くないものの、合格に必要な勉強時間はあまり多くはありません。財務の知識が全くない状態から勉強を始めたとしても、50時間程度で合格が可能です(稀に一夜漬けで試験に臨む人がいますが、一夜漬けで合格するのは難しいのでやめておきましょう)。これは、平日1時間・休日3時間の勉強をすれば約1ヶ月で達成可能な時間です。(もともと簿記等を学習しており、財務に関する知識がある方であれば問題演習を数回繰り返せば合格レベルに達すると思います)。なので決して難易度の高い試験ではありません。タクスの教材を使って、ぜひ1発合格してください!
財務3級は、基本的に過去問と類似する問題が多く出題されます。しかし、出題の仕方が変わると途端に正答率が下落します。直近3回の試験のうち、正答率が30%以下であった問題は以下になります。
| 試験日 | 論点 |
| 2023年6月 | ・当期製品製造原価の額の算出 ・社債 ・営業外損益の区分に記載される項目の組合せ ・収益認識に関する会計基準 ・ROE の算出 |
| 2023年3月 | ・税効果会計 ・為替差損益の額の算出 ・自己株式の処分の仕訳 ・営業活動によるキャッシュ・フローの額の算出(間接法) |
| 2022年6月 | ・営業外損益に該当しないもの ・有価証券の決算整理仕訳 ・法人税等調整額の仕訳 |
特に計算問題は、切り口の異なる問題が出題されると正答率が低下する傾向にあるため、「なぜこの公式を用いるのか」「ここでは何を計算したいのか」を考えて勉強して、各論点の計算を理解することが必要です。
通常方式とCBT方式の違い
受験方法は、通常の受験方法と全国のテストセンターの中から好きな日時と場所を決めコンピューターで受験するCBT方式の2つがあります。それぞれの概要は以下の通りです。
| 通常 | CBT方式 | |
| 受験料 | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) |
| 持込品 | 受験票、筆記用具(HB程度の鉛筆・シャープペンシル、消しゴム)、 電卓(1台のみ使用可。ただし、金融計算電卓、関数・メモ機能付は不可) | 受験票 |
| 出題形式 | 五答択一式(マークシート) | CBT五答択一式 120分 |
| 科目構成 出題数 | 財務諸表 30問 財務分析 20問 | 財務諸表 30問 財務分析 20問 |
| 合格基準 | 100点満点中60点以上(試験委員会にて最終決定される) | 100点満点中60点以上 |
| 正解発表 成績通知 | 正解は試験実施3日後(原則として17:00以降)に銀行業務検定協会HPで公表。 合格した方には試験実施約4週間後から成績通知書と合格証書が送付される。 (解答用紙の返却はされない) | 即時判定。 試験終了後にスコアレポート・出題項目一覧が配布される。 合格者は受験日の翌日以降にマイページから合格証書をダウンロード可能。 |
最新の試験日
通常の受験方法では、年2回(毎年6月と3月)試験が行われます。次回以降の試験日で日程が確定しているものは以下となります。
| 実施日 | 開始時刻〜終了時刻 |
| 2025年3月2日(日) | 13:30~15:30(午後) |
財務3級は、何かと他の資格(法務3級など)の試験日程と被ることがあります。そのようなタイミングでダブル受験をする方がいますが、個人的にはあまりおすすめしていません。
というのも、ダブル受験をすると受験する試験両方とも十分な勉強時間を確保できず、全落ちになるリスクがあるためです。まさに「二兎追うものは一兎も得ず」の状態です。そのため、1日1試験ずつ、着実に受験していく方がおすすめです。
ちなみに、銀行業務検定の中で、CBT方式に対応しているものは以下の試験です。財務2級はCBT方式に対応していないため注意してください。
・財務3級
・財務4級
・法務3級
・法務4級
・税務3級
・税務4級
・年金アドバイザー3級
・年金アドバイザー4級
・相続アドバイザー3級
・信託実務3級
・事業性評価3級
・事業承継アドバイザー3級
・DXサポート
試験範囲は以下の通りです。全部を取り扱うとキリがないため、本サイトでは出題頻度が高い論点を中心に取り扱っていきます。
- 企業会計原則同注解
- 会社法 会社法施行規則および会社計算規則
- 資産と負債の分類基準
- 貸借対照表の意義・表示区分
- 資産の会計
現金預金 / 売上債権(売掛金、受取手形、手形の裏書と割引、破産更生債権) / その他の債 権(貸付金、未収入金, 前払金、立替金、仮払金) / 貸倒損失と貸倒引当金 / 有価証券 / 棚卸資産 / 有形固定資産 / 無形固定資産 / 投資その他の資産 / 繰延資産 / 減価償却 など - 負債の会計
仕入債務(買掛金、支払手形) / その他の債務(借入金、未払金、前受金、預り金 受金) / 負債性引当金 / 社債 など - 純資産の会計
株主資本(資本金、資本剰余金、利益剰余金, 自己株式) / 評価換算差額等 / 新株予約権など - 損益計算書の意義・表示区分
- 収益
- 費用
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 連結財務諸表 (連結計算書類)
- 各種の会計基準等
外貨建取引等会計処理基準・同注解/退職給付に係る会計基準 / 税効果会計に係る会計基準 / 金融商品に関する会計基準 / 1株当たり当期純利益に関する会計基準 / 固定資産の減損に係る会計基準/役員賞与に関する会計基準など
- 収益性分析
総資本経常利益率/ROE / 各種の売上高利益率 / 売上原価率 / 売上高対販売費・一般管理費比率 / 売上高純金利負担率 など - 回転率と回転期間
- 損益分岐点分析
固定費と変動費 / 限界利益率 / 損益分岐点売上高 / 損益分岐点比率 / 経営安全率 など - 利益増減分析
- 生産性分析
付加価値額 / 付加価値率 / 労働生産性 / 労働分配率 / 労働装備率 など - 安全性分析
流動比率 / 当座比率 / 固定比率 / 固定長期適合率 / 自己資本比率 / インタレスト・カバ レッジ・レシオ など - 資金表
資金運用表 / 資金繰表 / 資金移動表 - キャッシュ・フロー計算書
- 資金需要
①授業動画を視聴する
こちらのリンク先にある授業を視聴します。各授業は出題頻度別にレベル分けしてあります。
☆☆☆☆☆:毎回約3問出てる!☆☆☆☆:毎回約2問出てる!☆☆☆:ほぼ毎回出てる!
☆☆:出題確率1/2くらい
☆:出題されてはいるけども…
②演習問題を解く
こちらのリンク先にある演習問題を解きます。
また、YouTube Shortsでも毎日問題を投稿しています!(YouTube shortsの問題は、理論問題のみです。通勤時間等のスキマ時間で活用してください)
③問題集・過去問を解く
「演習問題だけでは問題数が少なくてちょっと不安…」「合格可能性をもっと上げたい!」という方は市販のテキスト・問題集を見ておくといいでしょう。おススメのテキスト・問題集は下記「おすすめ教材」で紹介しています。
・公式テキスト
第1編 財務諸表
1. 計算書類
2. 企業会計原則
3. 貸借対照表
4. 流動・固定の分類基準
5. 流動性配列法
6. 受取手形
7. 有価証券
8. 棚卸資産
9. 有形固定資産
10. 減価償却/ほか
第2編 財務分析
1. 総資本経常利益率
2. 売上高経常利益率
3. 総資本回転率
4. 売上債権回転率・回転期間
5. 棚卸資産回転率・回転期間
6. 損益分岐点分析
7. 損益分岐点売上高
8. 目標売上高
9. 損益分岐点比率と安全余裕率
10. 売上総利益の増減分析/ほか
財務3級試験の公式テキスト。各論点の内容もちろん、重要性に関しても解説されています。
「授業動画だけでは不安…」「もっと網羅的に学習をしたい!」「紙のテキストが欲しい!」という方は購入を検討してみてもいいかと思います。
・問題解説集
第1編 財務諸表
1. 財務諸表の仕組み
2. 会計制度
3. 資産・負債の区分表示
4. 売上債権
5. 有価証券
6. 棚卸資産
7. 固定資産
8. 減損会計
9. リース会計
10. 減価償却
11. 繰延資産
12. 引当金
13. 退職給付会計
14. 流動負債・固定負債
15. 純資産(資本)
16. 製造原価
17. 営業損益計算
18. 経常損益計算
19. 純損益計算
20. 税効果会計
21. 外貨建取引
22. 連結財務諸表
23. 粉飾・利益操作 ほか
第2編 財務分析
1. 資本利益率
2. 売上高利益率
3. 回転率・回転期間
4. 配当性向・総還元性向
5. 損益分岐点分析
6. 利益増減分析
7. 生産性分析
8. 安全性分析
9. 資金運用表
10. 資金移動表
11. 資金繰表
12. 運転資金・設備資金
13. キャッシュ・フロー計算書 ほか
過去の試験問題について簡潔に解答と解説が記載されています。解説内容が少し分かりにくいので、タクスの授業動画と併用する使い方がおススメです。
・直前整理70
1. 会計制度
2. 貸借対照表
3. 損益計算書
4. 株主資本等変動計算書
5. 残高試算表
6. 新会計基準
7. 連結財務諸表
8. その他
9. 収益性分析
10. 生産性分析
11. 静態的安全性分析
12. 動態的安全性分析
13. 運転資金と設備資金
14. キャッシュ・フロー計算書
15. その他
試験直前に重要論点を復習したい時に利用します。重要な論点がコンパクトにまとまっているので、短時間でこれまでの学習の総洗いをすることが可能です。ただ、あくまで前述のテキストや問題集をしっかりやっていることが、前提として作られているので、「これだけやっとけば大丈夫(^^) 」というものではありません。その点ご注意ください。
- 試験の申込はどこからできますか?
- 試験の申込はこちらからできます。ただ、お勤めの会社で指定の申込方法がある場合には、そちらに従ってください。
- 銀行員ではないのですが、銀行業務検定 財務を取得する意味はあるのでしょうか?
- 結論から言うとあまり無いと思います。確かに銀行業務検定 財務3級を受験することで、財務に関する教養を深めることはできますが、銀行業務検定 財務3級の学習内容は銀行業に関連したものが多いです。基礎的な財務の教養を深めたいのであれば、簿記3級などの別の資格を受験することをおすすめします。
- 財務3級の次に受けるべき試験は何がありますか?
- 財務3級を受ける方が次に受ける科目としては、税務3級や法務3級があります。
この他に、財務2級という財務3級の上位試験もございます。財務2級は記述式の試験であり、難易度もそれなりに高い試験となっております。そのため、財務3級以上に各論点の理解が重要になってきます。
- 今回の銀行業務検定 財務3級に落ちてしまったのですが、次の回で再受験が可能でしょうか?
また財務3級に合格していなくても、財務2級を受験することはは可能でしょうか? - 不合格の場合は、次回の試験を再受験することができます。あきらめずに何度も受験しましょう。
財務3級に合格していなくても、財務2級を受験することは可能です。しかし、財務2級は記述式の試験であり、各論点の内容の理解が必要となります。また当然、財務3級よりも難易度が高いです。そのため、まずは財務3級に合格してから、財務2級を受験することをおすすめします。
 タクス 銀行員の学校
タクス 銀行員の学校